HPSトレーニングは数年前から少し話題になっているトレーニング方法で僕は「筋肉あるある」さんの紹介動画で知った。以下にURLを貼っておくので気になる方はそちらをどうぞ
僕も実際に爆伸びしたプログラムなのでここでも詳しく解説していきます
参考にしたYouTube解説動画:
https://youtu.be/oqiscgy4XO8?si=RyEBWfnDk7VGsuhP
はじめに
HPSは「Hypertrophy(筋肥大・ハイボリューム)」「Power(パワー)」「Strength(筋力)」の頭文字を取った、週3構成のトレーニングプログラム。
1種目につき3種類の異なる刺激を週の中で与える構成で、筋力・動作・神経系すべてに段階的な適応を促すことができる。
シンプルな内容ながら、筋トレ中級者にとって“迷わず取り組める強力な型”として非常に効果的。
各セッションの詳細解説
🟩 H:Hypertrophy(筋肥大)
- 内容:1RM/75% × 8回 × 5セット(全週固定)
- 目的:筋肥大・フォームの反復・動作の再現性強化
このセッションでは、筋肉の断面積を増やす中重量ボリュームと、同じ動作を繰り返すことでの“動作の安定”を狙う。
反復によって無意識に近い動作が身に付くほか、筋力向上の土台である筋量増加もここで確保する。
Hの日は単に筋肉を追い込むだけでなく、「この週はこう動く」という神経的なパターンを覚え込ませる意味も強い。結果として、PやSで扱う高重量でもフォームが崩れにくくなる。
また、セット数が多いため、集中力や疲労管理のトレーニングにもなる。地味だけど“積み重ね”として超重要なパート。(正直一番きついのがこの日)
文献ではこの日は調整の幅があるようだが今回の解説では固定とする
🟦 P:Power(パワー)
- 内容:高重量シングル(1回)× 4〜5セット(週ごとに重量漸進)
- 目的:神経系の活性化・動作速度の強化・出力感覚の調整
この日は“速く丁寧に挙げる”ことがテーマ。MAX重量で潰れないためには、動作の初動スピードが重要になる。ここでは爆発的な挙上を練習する。
スティッキング(動作が止まりやすい“つっかかり”)
例:スクワットの切り替えしやベンチプレスの押しきり
これを乗り越えるには、最初の挙げ始めのスピードが不可欠。バーが止まる前に一気に通過させる神経系の反応を養うのがPセッション。
また、前後のH/Sよりもボリュームが軽めなため、疲労を抜くアクティブレスト的役割も果たす。
「Pって意味あるの?」と思われがちだが、MAX動作で潰れないための“予行演習”として超重要なセッション。負荷の高いHとSの間の回復パートでもあるのでこの日をおろそかにしてはいけない。意味があるかではなく意味を持たせるのが大切。
🟥 S:Strength(筋力)
- 内容:高重量 × 限界ギリ手前 × 3セット(週ごとに重量漸進)
- 目的:再現性のある最大出力の習得・精神的集中の強化・換算RM挑戦
この日は、1RMに近い高重量を扱いながら、崩れずに“出し切る”ことを意識する。(強くなっているかどうかはこの日で確認する。換算RMを伸ばす日)
潰れるまでやるのではなく、「フォームが崩れない限界手前で止めて正確にまとめる」ことがテーマ。潰さずに終えることで再現性が高まり、フォームも崩れにくくなる。
高重量でも同じ動作ができるかどうか、フォーム・集中・出力をすべて揃える必要がある。技術と気力の試される日。
出力のピークを目指す週の“勝負どころ”であり、HやPの土台があるからこそ安全に追い込める構造。
HPSの6週間進行表※%は1RMに対して
| WEEK | Hypertrophy(H) | Power(P) | Strength(S) |
|---|---|---|---|
| 1 | 75% × 8 × 5 | 80% × 1 × 5 | 85% × 限界回数 × 3set |
| 2 | 75% × 8 × 5 | 80% × 1 × 5 | 87.5% × 限界回数 × 3set |
| 3 | 75% × 8 × 5 | 85% × 1 × 4 | 90% × 限界回数 × 3set |
| 4 | 75% × 8 × 5 | 85% × 1 × 4 | 90% × 限界回数 × 3set |
| 5 | 75% × 8 × 5 | 90% × 1 × 4 | 92.5% × 限界回数 × 3set |
| 6 | 75% × 8 × 5 | 90% × 1 × 5 | 95% × 限界回数 × 3set |
H→P→Sの順番を守る理由
この順序には「ボリューム(筋肥大)→ 神経 → 出力」のように段階的な積み上げの意図がある。
- Hでフォームと筋量を整える(基礎)
- Pで神経系を活性化し、疲労を抜きながら準備(調整)
- Sでピーク出力に挑む(実践)
実施時の注意点
- セッションの意図を混ぜない(例:Pの日にボリュームを足さない)
※補助種目は追加は自由。余裕があれば1~2種目補助をやるといいが、Pの日は回復と割り切るべきだと個人的には思う。また、初めてHPSに取り組む人はまずは補助種目無しで完遂を目指そう。 - スクワットとベンチなど複数種目を並行する場合、HとSが同日に被らないよう調整(後半の種目の精度が疲労でかなり落ちます。Pとの被りはあり)※ベンチHの後にスクワットSをやるとすでにベンチで体力使ってしまっているので本来のAMRAPが計れないことがあるためHとSは別日設定がおすすめ。
- 疲労の蓄積や回復力を確認しながら進める(特にS後からHは2日以上空けることを推奨)
まとめ
HPSは“シンプルな構造で初級~中級者が強くなるための型”として非常に優秀。
筋力を伸ばすだけでなく、動作精度・疲労管理・ピーク設計の概念も自然に身に付く。
これを軸にピリオダイゼーションや非線形プログラムに移行していくとスムーズに移行できます。
実際に自分が運用して役3ヶ月でスクワット+30kg、ベンチプレス+15kgUPしたやり方も別記事にありますのでよかったらそちらもどうぞ
プログラムを運用して今日も重力に抗っていきましょう!
アンチ・グラビティ!!

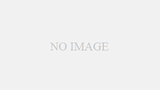

コメント