結論:アクティブレスト=“動かしながら回復する”時間
たとえば──
部活や競技スポーツをやっていた人なら、一度はこんな経験があるはずです。
「今日は気分転換に、別のスポーツやるか」とバスケ部の人がサッカーをしたり、陸上部の人が軽く球技をやったり。
あれこそ、まさにアクティブレストの原型です。
メインの負荷から一歩引いて、体を動かしながら疲労を抜く。
休みつつも“リズム”や“感覚”は保つ。
それが現代のトレーニング理論においても、有効な方法として整理されています。
筋肉をつけるにはハードなトレーニングが不可欠ですが、それを“続けられる状態”を保つことこそが最重要です。
実は、多くの人が「休むのが怖い」「サボりたくない」と思うあまり、回復を軽視して逆に伸び悩んでしまいます。
アクティブレストは、そうした“休めない人”にも有効な回復戦略です。
アクティブレストとは?
アクティブレストとは、完全休養を取らずに軽度の運動を行うことで、回復を促進する方法です。
以下のような活動が典型的な例です:
- 軽いウォーキングやジョギング
- フォーム確認だけのベンチプレス・スクワット(50%1RM以下)
- ストレッチやモビリティドリル
- 有酸素バイク、スイミング、ヨガなど低強度の全身運動
これらは血流を促し、疲労物質の除去や自律神経の調整、可動域の維持に役立ちます。
目的は「トレーニング効果」ではなく回復とリズムの維持です。
実際、アクティブレストは以下のような効果が報告されています:
- 筋肉の血流促進による老廃物の排出向上
- 筋肉痛の回復促進(DOMS対策)
- 神経系のリズム維持による翌日のパフォーマンス安定
- メンタル面での疲労感の軽減
特に、週5以上トレーニングをしている人にとっては「止まらず整える」手段として非常に有効です。
ディロードとの違い
アクティブレストと混同されがちなのがディロードです。
どちらも「疲労を抜くために負荷を下げる」という点は共通していますが、その性質と目的は明確に異なります。
| 比較項目 | アクティブレスト | ディロード |
|---|---|---|
| 実施目的 | 心身の回復とリズム維持 | パフォーマンス回復・次サイクル準備 |
| 実施タイミング | OFF日や不定期に | サイクル間や明確な設計に基づいて |
| 種目 | 通常とは異なる運動も多い | 通常のトレーニング種目を軽く継続 |
| 対象レベル | 初心者~上級者までOK | 中級者以上に推奨される傾向 |
つまり、アクティブレストは“補助的”で自由度が高く、ディロードは“計画的”に行う休養戦略です。
活用タイミングとおすすめ内容
▼おすすめのタイミング
- トレーニング後に疲労感が強いが、完全休養にはしたくない日
- 怪我や違和感があり、完全トレーニングは避けたい期間
- サイクルの合間(ディロードの週)に補助的に取り入れる場合
- メンタル的に「何もしないと不安」な時のルーティン維持
▼おすすめ内容例
- 20〜30分のウォーキングや有酸素バイク
- ロールアウト、ダイナミックストレッチ、モビリティ系
- 50%以下のフォーム練習(ベンチ、スクワット、プル系など)
- 軽いサーキット(バーピーなし、全身バランス系)
ポイントは、「絶対に疲労を残さない強度」で行うことです。
アクティブレストでやってはいけないこと
一番よくある失敗は、「軽くのつもりが普通に追い込んでしまう」ことです。
- 知らずにHIITをやってしまう
- 60%1RMを超える重量でセットを組む
- サーキット形式でゼェハァ言うまで追い込む
これでは完全に逆効果。
疲労を抜くどころか、回復阻害・集中力低下・ケガのリスク増大にもつながります。
アクティブレストのゴールは「明日また頑張れる体調を保つこと」であって、成長刺激ではありません。
まとめ:アクティブレストは「続けるための技術」
アクティブレストは、特に次のような人にとって効果的です
- 休むのが不安で、つい毎日動いてしまう人
- 疲れているはずなのに「今日は何をすればいいか分からない」人
- トレーニング頻度が多く、疲労が抜けきらない傾向がある人
こうしたタイプの人ほど、アクティブレストを“戦略的に挟む”ことで、トレーニングを長く・強く続けやすくなります。
アクティブレストは、単なる“軽い運動”ではなく、継続と回復を両立させるための重要な手段です。
- ただの休養ではなく「軽く動いて血流を促す」
- 種目の選択や強度設定に注意すること
- サイクル設計に組み込むよりも“補助的に使う”のが基本
うまく取り入れられれば、ケガや停滞のリスクを下げながら、トレーニングを長く続ける土台になります。
「何もしない」ではなく「少し動いて整える」。
それがアクティブレストの本質です。
うまく疲労と付き合いながら重力に抗っていきましょう!

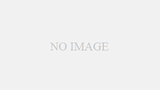
コメント