結論:RPEは“筋トレの正確さ”を高めるための指標
RPEという言葉を聞いたことはありますか?
トレーニング記録やプログラム解説でよく出てくる「RPE8」や「RPE9」といった数字(または@8@9という表現をする場合もある)
これは単なる感覚表現ではなく、負荷管理や疲労調整に使える“主観的な強度スケール”です。
正しく使えば、「オーバーワークを防ぎつつ最大限に追い込む」ことも可能になります。
この記事では、RPEとは何か?どのように使うのか?について、初心者でもわかりやすく解説します。
RPEとは何か?
RPEとは Rate of Perceived Exertion(主観的運動強度) の略で、「今のセット、あと何回できそうか?」という感覚を数値化したものです。
筋トレ用のRPEは「10段階評価」で表され、以下のように定義されます:
| RPE | 残り回数(RIR) | 感覚の目安 |
|---|---|---|
| 10 | 0回(限界) | ギリギリで1回完遂。もう無理。 |
| 9.5 | 0〜1回 | もう1回できるか微妙 |
| 9.0 | 1回 | 確実にあと1回はできた |
| 8.0 | 2回 | 余裕を残しつつ刺激あり |
| 7.0 | 3回 | 軽めだがフォーム練習には適正 |
| 6.0以下 | 4回以上 | ウォームアップ、調整用 |
元は有酸素運動用のボルグスケール(6〜20段階)ですが、筋トレでは 「Reps in Reserve(RIR)」=残り回数 による変換で使われるのが一般的です。
RPEを使うメリット
1. オートレギュレーション(自動調整)が可能
筋トレは日によって調子は変わるもの。RPEを使えば、「調子の良い日は少し重く、悪い日は少し軽く」自然に調整できます。
2. 無理な失敗を避けやすい
常にRPE10で攻めると、フォーム崩れや関節への負担が増えます。RPE8〜9でコントロールすれば安全に限界付近へアプローチ可能。
3. 疲労と回復の管理ができる
プログラムにおける“波”を作りやすく、過負荷と回復を交互に調整しやすくなります。
よくある誤解と注意点
- 「RPE=ただの感覚だから信用できない」→ ×
→主観ではあるが、経験と記録で精度は上がる。初心者こそ意識して運用する価値あり。 - 「RPE10までやらないと意味がない」→ ×
→RPE8でも十分な刺激を与えられる。常にRPE10だとオーバーワークに陥りやすい。
RIRとの関係と換算
RIR(Reps in Reserve)は「あと何回できそうか?」をそのまま数値化したもので、RPEと1対1で換算できます。
| RIR | RPE |
|---|---|
| 0回 | RPE10 |
| 1回 | RPE9 |
| 2回 | RPE8 |
| 3回 | RPE7 |
どちらを使っても構いませんが、RIRは明示的、RPEは包括的なニュアンスがあると理解しておくと良いです。
種目別の運用アドバイス
- BIG3(スクワット・ベンチ・デッド):RPE運用に向いている。トップセットやボリューム管理に。
- 小筋群(アーム系など):誤差が出やすい。回数やパンプ感を優先してもOK。
RPEを正しく使うには?
最初のうちは、自分の感覚と実際の動作にズレがあるかもしれません。
そのため、以下の方法で精度を上げていきましょう。
▼ 初心者へのおすすめステップ
- 動画撮影して客観的に確認
→「RPE8と思ったがフォームが崩れていた」など発見できる - 記録を残す(重量・回数・RPE)
→変化の傾向や“自分の限界”の目安が可視化される - 実力が安定するまではRPE8を基準に
→疲労を溜めすぎず、かつ成長を促す安全ライン
私の感覚ではベンチもスクワットも挙上スピードが落ち始めた時がだいたいRPEは7~8くらいになるかな?と思います。粘りが出ると8~9の間におさまるかな?という感覚です
まとめ:RPEは“主観と客観の橋渡し”
RPEは単なる数字ではなく、「自分の今の限界を自分で管理するためのツール」です。
重さに頼りすぎず、自分の身体と向き合う習慣をつくることで、パフォーマンスも効率も大きく変わります。
- 調子を見ながら“日々の強度”を調整できる
- 限界ではなく“限界手前”で止める練習ができる
- 記録と照らし合わせて“再現性のある強さ”が作れる
RPEは、競技者だけでなく、筋トレを長く続けるすべての人にとって有効なスキルです。
「感覚」こそ、正しく磨けば最強の武器になる。

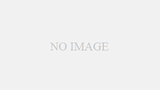
コメント