結論:RMは“目的に合わせた重さ設定”の基準
筋トレで「5RM」や「10RM」という言葉、聞いたことありませんか?
これは“何回できるかギリギリの重量”を表す用語で、RMとは「Rep Max(最大反復回数)」の略です。
RMを使うことで、「筋肥大向きの重さ」「筋力向上に適した回数」などが明確になり、トレーニングの設計が非常に効率的になります。
この記事では、RMの意味から実践での使い方、RPEとの組み合わせ方まで解説します。
RM(Rep Max)とは?
RMとは “Repetition Maximum” の略で、「限界まで行った時にできる回数」を示します。
たとえば:
- 1RM:1回しか挙げられない最大重量(限界重量)
- 5RM:5回が限界の重量
- 10RM:10回で限界を迎える重量
つまり、RMの数が小さいほど重く、大きいほど軽い重量になります。
これはすべての種目に共通する考え方です。
RPE・RIRとの違いと関係
- RM:実際の限界値(設定基準)
- RPE:主観的な強度評価(その日の感じ方)
- RIR:残り何回できそうか?(Reps in Reserve)
例:
あなたが100kgで5回やって「これ以上は無理」と感じた → 5RM
同じ100kgで「あと1回できそう」→ RPE9(RIR1)
つまり、RMは「どのくらいの重さを使うか」、RPEは「その重さで何回やるか」の指標になります。
RMを使うメリット
- 目的に合った“ちょうどいい重さ”を選べる
→ 筋肥大:8〜12RM、筋力向上:3〜6RMなど - プログラムの精度が上がる
→ HPS、Smolov Jr.、5/3/1法などのプログラムはRMベースで構成されることが多い - トレーニングの“狙い”を明確にできる
→ 回数や刺激の意図を数値で管理しやすくなる
RM換算表(目安)
以下は、1RMを基準にしたおおよその換算表です(疲労状態や種目により変動あり)。
| RM | %1RM目安 | 目的の目安 |
|---|---|---|
| 1RM | 100% | 最大筋力、試技練習 |
| 3RM | 約92〜93% | 高強度、出力トレーニング |
| 5RM | 約87〜89% | 筋力+筋量両立期 |
| 8RM | 約80〜82% | 筋肥大の中心強度 |
| 10RM | 約75〜77% | 筋肥大、フォーム習得 |
| 12RM | 約70〜73% | パンプ狙い、関節負荷軽減 |
▼ 応用:換算MAX(推定1RM)の活用法
RMを使えば、MAXを実測しなくても推定できるのも大きなメリットです。
例えば:
- 80kgを5回挙げた場合 → 80kg ÷ 0.87 ≒ 推定1RM 92kg
- 60kgを10回挙げた場合 → 60kg ÷ 0.75 ≒ 推定1RM 80kg
これを使えば、頻繁に1RM測定しなくても、成長の可視化やプログラム設定が可能になります。
RMとRPEを組み合わせるとどうなる?
RMは「限界値」、RPEは「そこまで追い込むかどうか」です。
この2つを組み合わせることで、より柔軟で戦略的なトレーニングが可能になります。
たとえば:
- 5RM(=5回限界の重量)をRPE9で使う
→ あと1回残して4回で止める(=刺激を残して疲労を抑える) - 10RMをRPE8で使う
→ 本来10回できる重量を8回で止める(=パンプ感を得ながらも余裕を持つ) - 実数値の1RMより安全に換算MAXが図れる
→例:ベンチプレス100kgを一回上げてあと一回余裕がある=RPEは9で2RM換算なので1RM換算は105kgになる
▼ RM × RPE対応表(目安)
| 目的 | 使用重量 | 回数目安 | RPE目安 |
|---|---|---|---|
| 筋力向上 | 85〜95% | 2〜5回 | RPE8.5〜9.5 |
| 筋肥大(中重量) | 75〜85% | 6〜10回 | RPE8〜9 |
| 筋肥大(高レップ) | 65〜75% | 10〜15回 | RPE7.5〜8.5 |
| 再現性・調整 | 60〜70% | 3〜6回 | RPE6〜7(フォーム練習) |
このように、RMで設定した重量をその日の調子に合わせてRPEで微調整するのが理想的です。
RMを正確に測るには?
▼ 実測する方法
- 1RMを測るときは、十分なアップ+安全確保(スポッター)
- 高回数(例:5RM〜10RM)は、無理なく測れる範囲で設定可能
初心者や中級者は、実測は控えめに、推定と感覚を組み合わせるのが安全です。
まとめ:RMは“自分に合った強度”を知るための基準
RMを理解することで、以下のようなことが可能になります:
- 「この重量は軽いのか、重いのか?」が明確になる
- 「この回数で何を狙うのか?」を目的別に整理できる
- 実測と推定を組み合わせて、トレーニングの“精度”が上がる
さらに、RPEと組み合わせることで「設定値+その日の体調」で現実的かつ柔軟なトレーニングが組めるようになります。
筋トレをただの“頑張り”で終わらせず、戦略と数字で成長を加速させたい人には、RMという考え方は欠かせません。

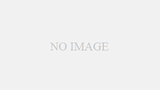

コメント